〜目的を見失う組織が陥るワナ〜
はじめに:ルールが目的化した瞬間、組織は止まる
「ルールだから守る」
一見、真面目で誠実な姿勢に見えるこの言葉。
でも、それが非効率や停滞の原因になっていることに気づいていますか?
本来、ルールやマニュアルは「目的を達成するための手段」であるべきもの。
ところが、いつの間にか手段が目的化してしまうことで、思考が止まり、改善の芽が摘まれ、組織全体が硬直化してしまうのです。
これは単なる現場あるあるではなく、組織論で「官僚制の逆機能」としても指摘されている深刻な問題です。
官僚制の逆機能とは?
社会学者ロバート・マートンが提唱した「官僚制の逆機能」という概念をご存じですか?
本来、組織の秩序や効率性を高めるために導入されたルールや仕組みが、逆に柔軟性を奪い、非効率を生んでしまう──そんな逆説的な現象です。
例えば、こんな状態が起こっていませんか?
- マニュアル通りでしか動けない
- 状況が変わっても、ルールは変えない
- 「なぜこのルールがあるのか」を誰も考えない
こうした状態が続くと、「考える力」を失った思考停止の組織が生まれてしまいます。
「目的を忘れたルール」が現場にもたらす弊害
次のようなシーン、心当たりはありませんか?
- 「とりあえず稟議を通さないと動けない」
- 「誰も読んでいない月報、形式だけ出し続けている」
- 「昔からそうだから」と変えることを諦めている
これらはすべて、“目的を見失ったルール”が現場に与える弊害です。
例えば:
- 稟議の目的は「リスク管理と意思決定の透明化」
- 月報の目的は「進捗や課題の共有と改善」
でも、その目的が意識されなくなると、ただの「やらされ仕事」と化し、形骸化していきます。そして、現場のやる気や生産性をじわじわと蝕むのです。
目的を取り戻すための3つの視点
では、どうすれば“考える組織”に変えていけるのでしょうか?
キーワードは、「目的を問い直す」ことです。
✅ 1. そのルールは、何のためにあるのか?
例:
- 勤怠管理 → 労働時間の適正把握と従業員の健康維持
- フォーマット統一 → 情報伝達の効率化とミス防止
常に「目的」をセットで考える習慣が、形式的な業務に意味を取り戻します。
✅ 2. もっと良い手段はないか?を考える
目的が明確になれば、それを達成する別の手段も検討できます。
例:
- 月報が目的を果たしていないなら、週1回の口頭報告やチャット共有で代替できるかもしれません。
ルールに縛られるのではなく、「目的を果たす手段」として再構築する視点が重要です。
✅ 3. 守るべきは“ルール”ではなく“目的”
時代や状況が変われば、手段も柔軟に変えるべきです。
“目的を守る”という価値観が現場に根づくと、ルールに縛られるのではなく、ルールを使いこなす組織文化が育ちます。
今日から始める!「考える組織」への一歩
組織の文化は、1人のアクションからでも変わっていきます。
まずは、小さな一歩を踏み出してみましょう。
💡 こんな行動から始めてみてください
- 定例会議で「このルールって何のためにあるんだろう?」と問いかけてみる
- 形骸化している業務を見直し、「このやり方なら目的をもっと果たせそう」と提案する
- 上司に相談する際、「目的と手段のズレ」という観点を伝える
おわりに:「考え続ける力」が、組織を変える
ルールを守ることは大切です。
でももっと大切なのは、「何のためにそのルールがあるのか」を常に問い続けること。
目的と手段を見失わない組織は、現場からアイデアと改善が生まれ、変化に強い文化が育ちます。
考え続ける組織が、成長し続ける組織になる。
今日からあなたの職場でも、その第一歩を踏み出してみませんか?

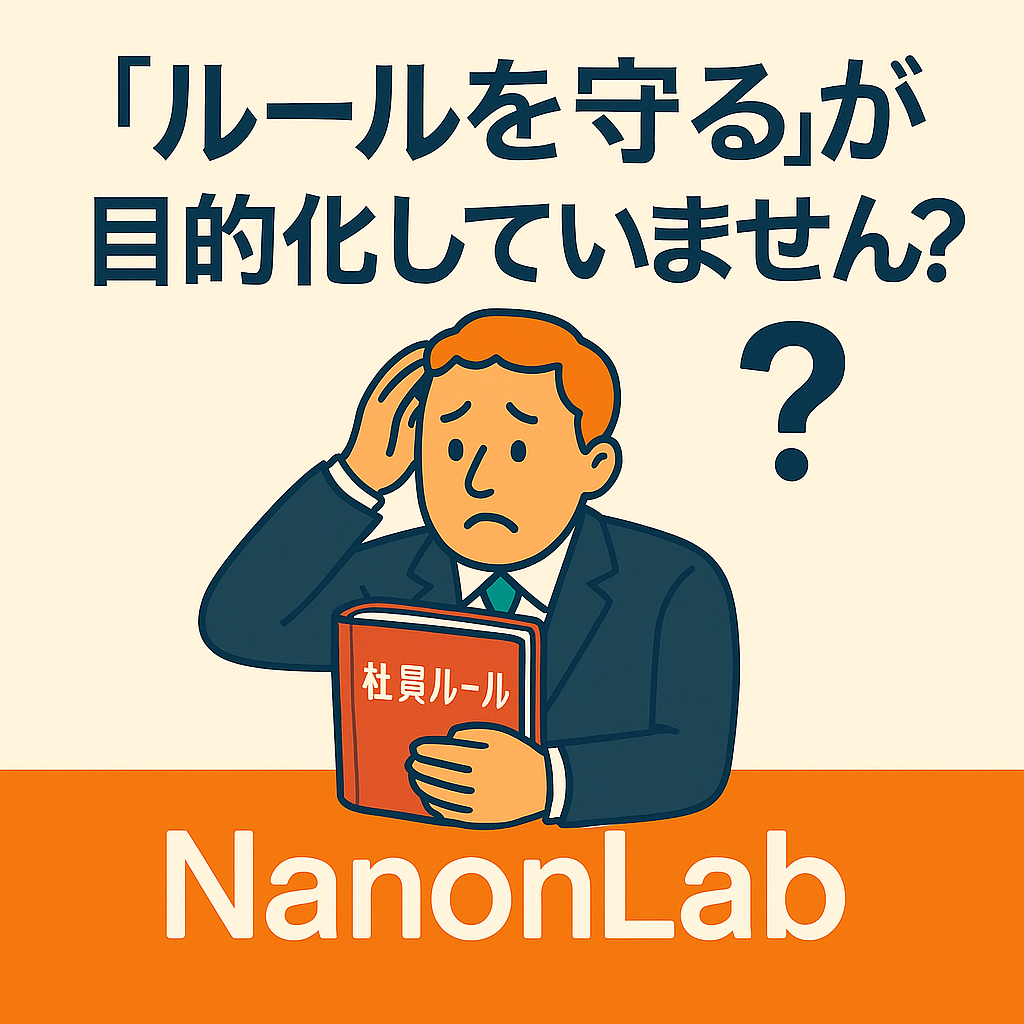

コメント