~小さな引っかかりが、大きな改善のヒントになる~
「なんか、ここだけムダ多くない?」をスルーしていないか
日々仕事をしていて、ふと「ん?これって…」と思う瞬間はありませんか?
誰かがエクセルで打ち直していたり、やたら承認が多かったり、前の工程に戻ってやり直していたり――。
でも、忙しさに流されてそれを深掘りせず、「まあそういうもんか」と受け入れてしまう。
それ、大きなチャンスを見逃しているかもしれません。
違和感とは、「何かおかしい」「なんとなくムダっぽい」という感覚のこと。
この“違和感”こそが、改善の出発点になります。
違和感は「システムのエラー」ではなく「人の感覚センサー」
業務フローの改善は、システムを入れる前に“気づく力”が要です。
現場にいて、毎日業務に向き合っている人ほど、実はたくさんの違和感を持っています。
例:
- なぜかいつもAさんにしか処理できないタスクがある
- 似た情報を、違う場所に2度入力している
- 本来1日で終わる処理に、なぜか3日かかっている
こうした小さなひっかかりを見逃さず、「なぜ?」と問い続けることが、真の業務改善につながります。
私が気づいた「違和感」からの改善ストーリー
私の職場でも、違和感から始まった改善がありました。
ある部署では、毎月末に「売上報告」を手入力でExcel集計しており、
担当者は3時間ほどかけて入力→印刷→上司に提出というフローを回していました。
ある時、その担当者がつぶやいたんです。
「これ、同じ内容が基幹システムにもう入ってるのに、手でやってるんだよな…」
調べてみると、なんとシステムから出力できるCSVを少し加工すれば、手入力は不要だったのです。
しかも、そのフォーマットで提出しても何の問題もなし。
それ以降、毎月の業務が3時間→10分になりました。
この改善のきっかけは、たった一言の“違和感”でした。
違和感を拾うための3つの視点
違和感を「ただの文句」で終わらせず、改善のヒントに変えるには、視点を持つことが大切です。
以下の3つを意識してみてください。
① 人に依存していないか?
→ 属人化している業務は、非効率やリスクの温床になりやすい。
② 二度手間が発生していないか?
→ データの再入力・転記・重複確認など、「同じことを2回していないか」に注目。
③ 無意識に「こういうもの」と受け入れていないか?
→ 形式・承認フロー・伝統的手順などを疑う視点を持つ。
違和感を“見える化”しよう
違和感を感じた瞬間にメモする。
週1回、「違和感日記」としてまとめてみる。
これだけでも、業務フローの中の改善ポイントが浮き彫りになります。
おすすめは、**「違和感ノート」**という習慣。
付箋でもスマホのメモでもOK。
「これってなんかムダかも?」を記録しておくだけで、改善活動の材料がどんどん貯まります。
まとめ:違和感は、現場にしか拾えない“改善の種”
業務改善の第一歩は、大きな仕組み変更やIT導入ではありません。
むしろ現場の“肌感”が持つ違和感にこそ、ヒントがあります。
大きな仕組み変更やIT導入の前に、実施しておく事で本当に必要な機能や判断基準も明確になります。
🔍 一言まとめ
「これってムダじゃない?」は、未来の業務改善レポートの“はじまりの一文”です。

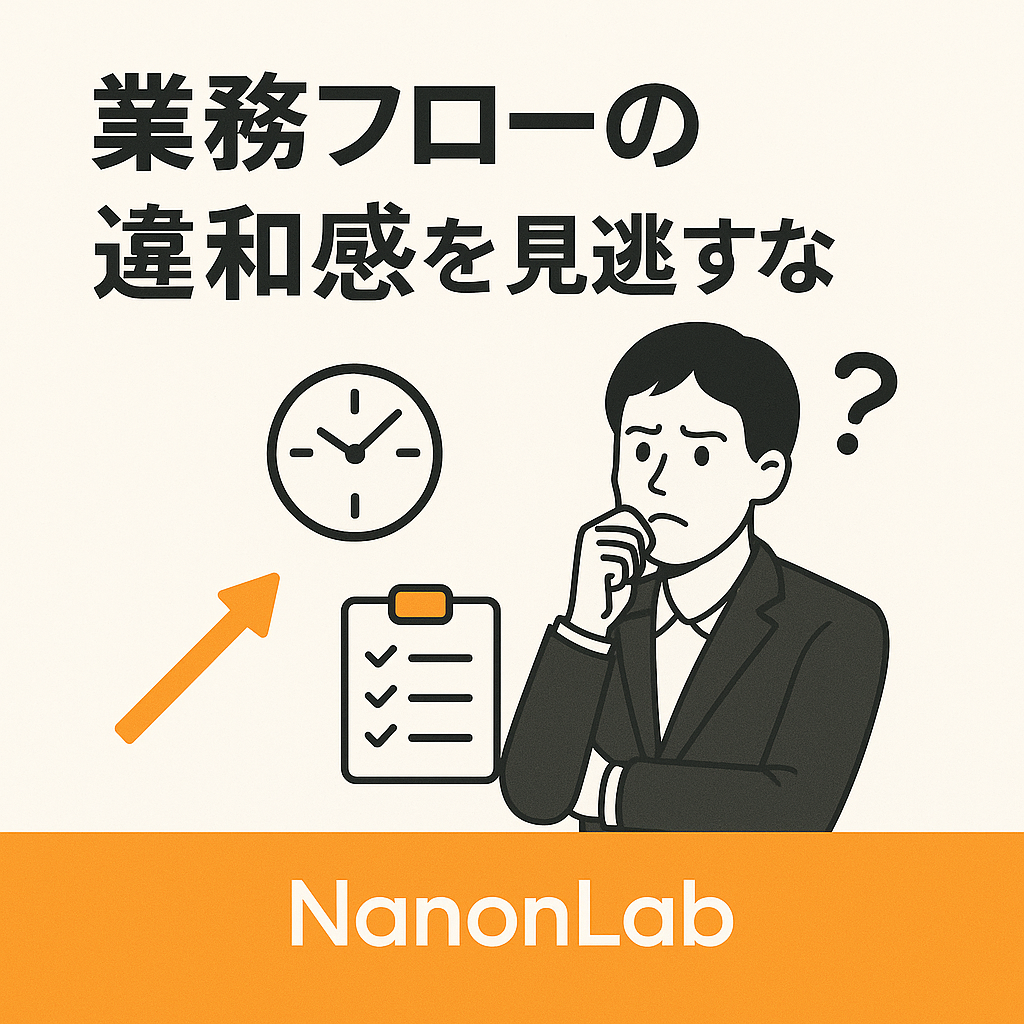
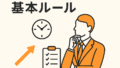
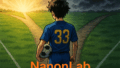
コメント